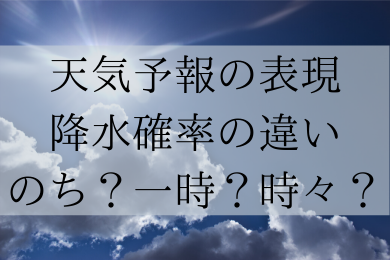まさに事実は小説よりも奇なり栗良平「一杯のかけそば」
昔、「一杯のかけそば」という童話がブームになりました。評判が評判を呼び作者の講演会では涙を流す人が続出。ところがブームはあっというまに去っていきました。その本当の理由とは。
栗良平「一杯のかけそば」あらすじ
札幌にあった一軒の蕎麦屋、名前は「北海亭」といいます。
大晦日になるとお母さんと子供が二人北海亭を訪れます。貧しい家なのか一杯のかけそばを三人でおいしそうに味わい、にこやかに大晦日を過ごして帰っていきます。
それをやさしく見守る蕎麦屋のおかみさんと、親子に内緒で半玉ぶんのお蕎麦をサービスしている店主。
数年間は大晦日のたびに美味しそうに一杯、子供の成長とともに二杯のそばを分けて食べる姿を見かけたのですが、やがて来なくなってしまいました。それでも毎年大晦日にはその家族が来るかもしれないと予約席を用意して待ち続ける北海亭の夫婦ふたり。
そしていよいよもう来ないのだろうと諦めそうになったある年の大晦日、ふらりとやってきたその客は…すっかり成長した子供とその母親だったのです。
話を聞くと実は滋賀県に家族が引っ越ししていたこと、小さかった男の子二人は長男が医師に、弟は銀行員として働いていること。長男が北海道で医師として働くことになり、父の墓参りも兼ねて母と3人で最高の贅沢、北海亭の年越しそばを食べようと蕎麦屋に来たのでした。
「よう、お二人さん!何をもたもたしているんだよ。十年間、大晦日の十時に来る予約席のお客を待っていたんだろ。ついに来たんだよ。お客さんをテーブルに通しなよ!」
女将は、八百屋のおやじさんの肩を叩くと、気を落ち着けて、大きな声で言いました。
「いらっしゃいませ!お待ちしておりました。こちらへどうぞ。二番テーブル、かけ三丁!」
「あいよ、かけ三丁!」
店主は、いつもの無愛想な顔を涙で濡らして答えました
貧しかった家族、子どもたちが立派に成長して戻ってきたお話に心を打たれる人が続出です。
泣けるストーリーから出てきたボロががっかりを生んだ
いや、お話としては人情味のある最高のストーリーです。単行本化はもちろんのこと映画化されるなど日本中を巻き込んだ大ブームになったのです。
作者の栗良平は実話童話の作者として講演会でもひっぱりだこ、ハンカチを握りしめて涙を拭う人が会場に溢れました。
が。ブームは一瞬にて消えます。それはたったひとことテレビで言ったのタモリの言葉だったとか。
- 150円あればインスタントのそばが3つ買える
- 「1杯のかけそば」ならぬ「涙のファシズム」だ
ほころびが出だすと早いもので、その後作者の詐欺疑惑などの悪い話がどんどん出てきて、あっという間にその作者は消えていきました。
実話童話と創作童話
この「一杯のかけそば」の話にはいくつかの問題が隠れていましたね。
まず第一に、「真実」とは何かという問題。この作品が嘘だと知ると、多くの人が裏切られた気持ちになったようです。しかし、創作の物語でも人々は感動を覚えるわけです。つまり、客観的な真実よりも、私たちが主観的に感じる「真実」の方が大切なのかもしれません。
次に、芸術作品の「価値」をどう判断するかという問題もあります。この話のストーリー自体は秀逸だと評価されていますが、作者の動機が疑われたことでなぜか作品の価値が失われてしまいました。芸術の価値は作品自体か、作者の意図か、それとも受け手の反応か。この事例は価値判断の難しさを物語っているのではないでしょうか。
さらに、感動を「商品化」することの是非という倫理的問題も浮かび上がってきます。作者は実話と偽って多くの人の涙を誘い、利益を得ようとしたかもしれません。感動を金儲けの対象にしてよいのか、芸術にはそこまでの自由があるのか。
短いストーリーですが面白い考察がいろいろとできる話でした。